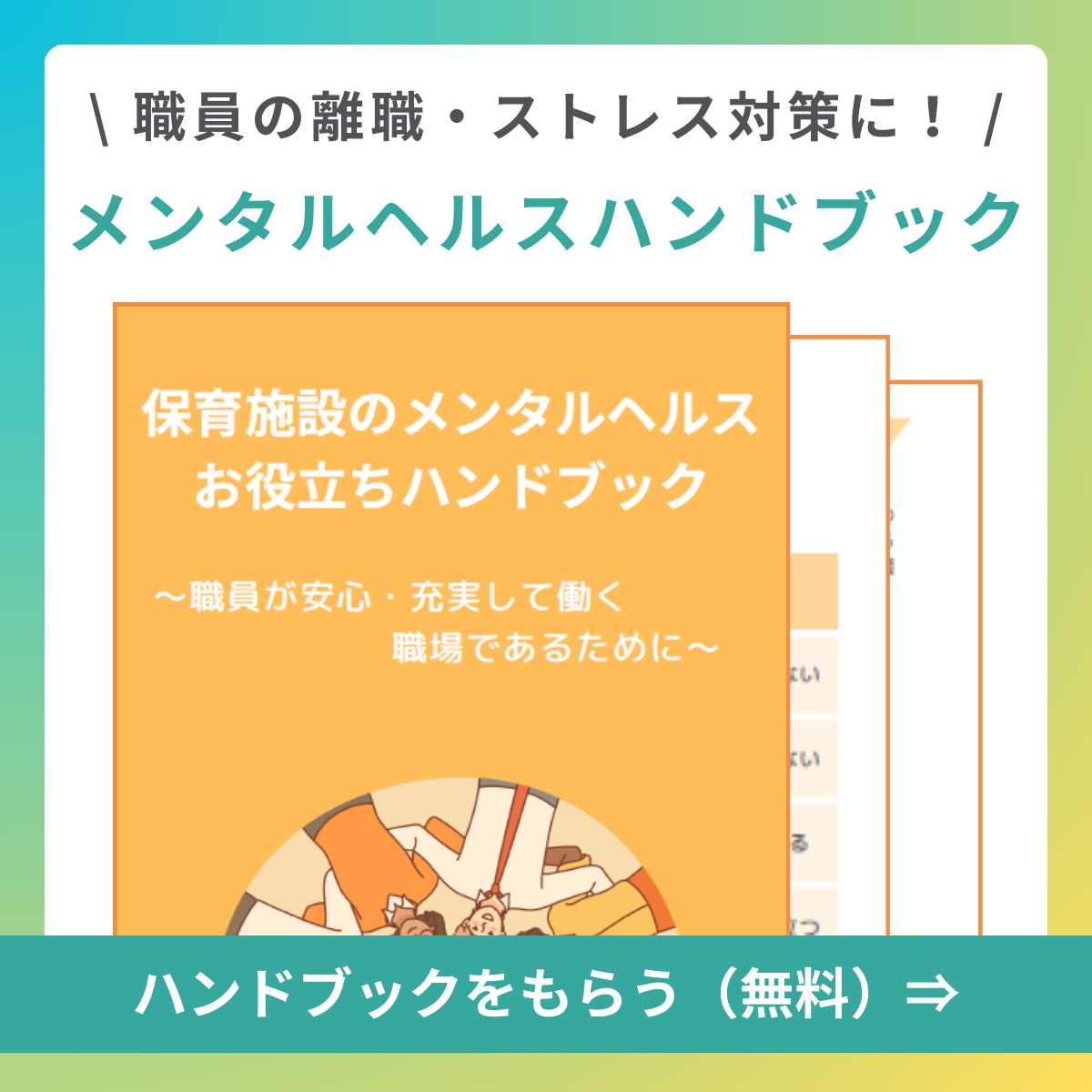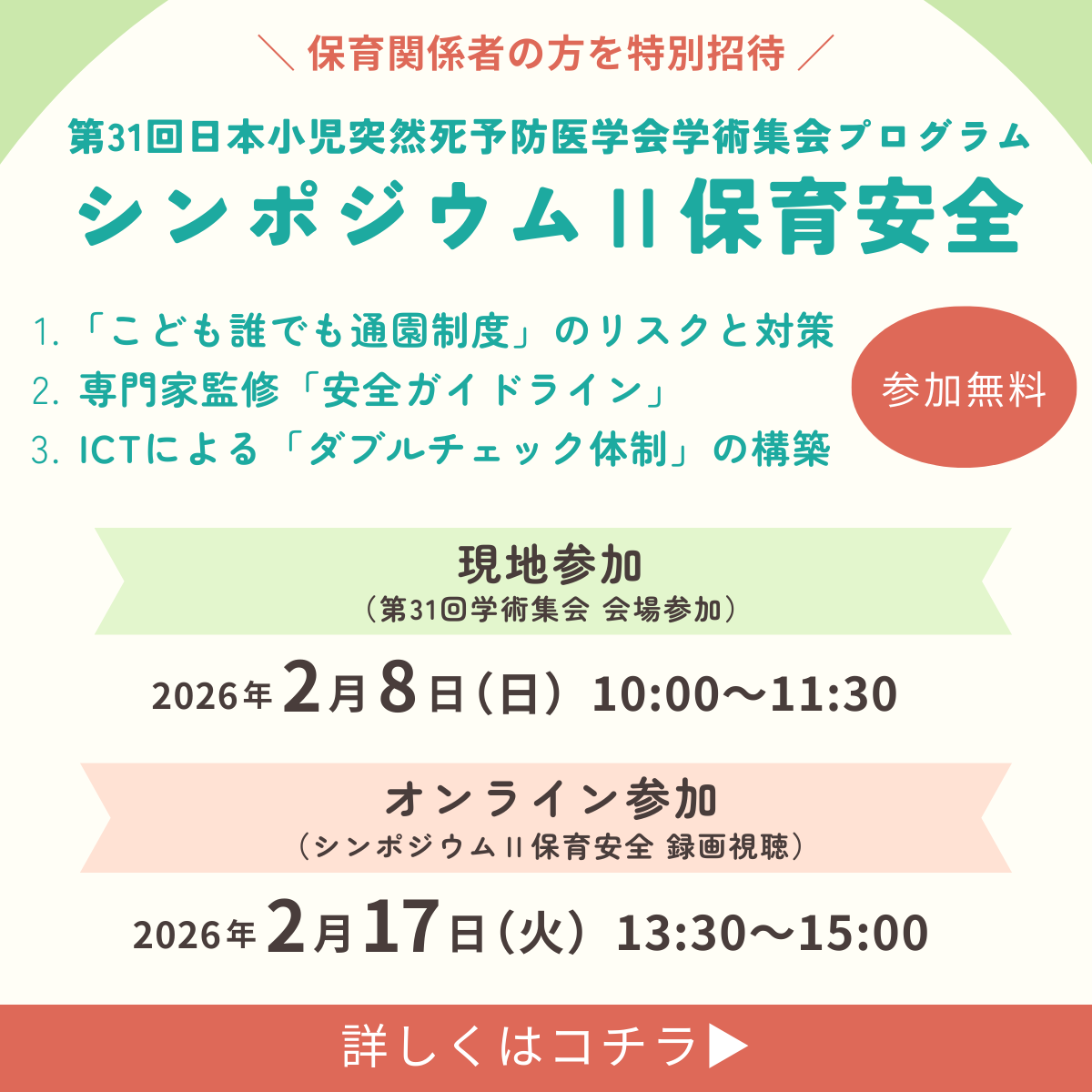保育士は、子どもたちの成長を見守るやりがいのある仕事ですが「思っていたより大変だった」と感じる瞬間も多くあります。子どもとの関わり方に悩んだり、保護者対応や人間関係にストレスを感じたりと、その悩みは子どもの年齢や役職によってさまざまです。
この記事では、保育士の仕事でよくある大変なことを紹介します。現場のリアルな声を通して、保育士の「大変さ」と向き合ってみましょう。
目次
保育士をやっていて大変なこと10選

保育士の仕事は、子どもたちの成長を支える重要な役割を担っていますが、多くの困難も伴います。ここでは、保育士をやっていて大変なことを紹介します。
1.子どもとの接し方に迷うときがある
保育士として働く中で、子どもへの接し方に迷う場面は多くあります。成長段階や個性に応じた対応が求められるため、一律の接し方では通用しません。
例えば、0〜1歳児は言葉で感情を表現できないため、泣き方やしぐさから気持ちを読み取る必要があります。表情や行動を細かく観察し、適切に対応する力が求められます。
2〜3歳児では、自己主張が強まりいわゆる「イヤイヤ期」に入ります。かんしゃくや拒否反応が多く、言葉で説明しても理解されにくいため、子どもの気持ちに寄り添いながら、根気強く対応しなければなりません。
4〜5歳児になると、友達とのトラブルや集団生活におけるルールの理解が課題になります。
2.人間関係のストレスで悩むときがある
保育士の仕事では、子どもとの関わりだけでなく、同僚や保護者との人間関係も重要です。特に職場の人間関係は業務の円滑さに直結し、ストレスの原因となることがあります。
例えば、保育方針や対応方法をめぐって同僚と意見が対立したり、保護者との意思疎通がうまくいかず誤解を生むことがあります。
保育はチームで進めるため、他の職員との連携が取れないと業務全体に支障が出ます。新しく着任した保育士にとっては、職場に溶け込むまでに時間がかかり、孤立感を覚えることもあるでしょう。
また、保護者からの細かな要望に過度に応えようとすることで、精神的に負担を感じることもあります。
3.保護者対応にプレッシャーを感じる場面がある
保育士にとって、保護者とのコミュニケーションは欠かせない業務の一つですが、その対応には大きなプレッシャーが伴います。特に、子どもに関する問題やトラブルが起きた場合には、保護者の不安や期待に対して的確に応じる必要があります。
例えば、園でのトラブルや行動上の課題を伝える際、保護者が感情的になることもあります。そのため、保育士は事実を冷静に伝え、改善策を具体的に提示する必要があります。
こうした対応には高度な説明力と配慮が求められます。また、「連絡帳にもっと詳しく書いてほしい」「全てのけんかを報告してほしい」といった要望や、理不尽なクレームに直面することもあります。
対応を誤れば信頼関係が崩れる恐れがあり、そのことが精神的な負担になることも少なくありません。
4.責任の重さに対して収入が見合わないと感じる
保育士は、子どもの命や成長を日々支えるという大きな責任を担っています。
安全管理や健康への配慮など、常に緊張感を持って業務にあたる必要があり、その負担は小さくありません。しかし、その責任の重さに対して、給与が見合っていないと感じる保育士は多くいます。
実際には、フルタイムで働いても手取りが10万円台というケースもあり、特に一人暮らしや子育て中の保育士にとっては生活の維持が難しい状況です。さらに、経験年数や役職に応じた十分な昇給が見込めない園も多く、努力やスキルが報われにくいという不満につながっています。
精神的・肉体的な負担も大きく、業務の多さや責任感からくるストレスが蓄積し、将来への不安を感じる保育士も少なくありません。このような状況が離職の一因となり、結果として人材不足を招いているのが現状です。
5.残業や持ち帰り作業が日常になっている
保育士の仕事は日中の保育に加え、勤務後も書類作成や連絡帳の記入、行事準備などの業務が続きます。これらの作業が勤務時間内に終わらず、残業や持ち帰り作業が常態化している保育現場は少なくありません。
こうした状況が続くと、疲労が蓄積し、プライベートの時間が圧迫されます。特に家庭を持つ保育士は、家事や育児との両立が難しくなり、精神的な負担が増す傾向にあります。
また、仕事と私生活の区別がつきにくくなり、十分な休息が取れずに体調を崩すケースもあります。疲労による集中力の低下は、業務ミスや職場内の連携不全を引き起こし、子どもへの保育の質にも影響を与える恐れがあります。
6.休みが取りづらくリフレッシュできないことがある
保育士は、子どもの安全と成長を見守る責任がある一方で、休みが取りづらい職種です。
保育園では人員に余裕がないことも多く、急な休みに対応できる体制が整っていない場合があります。例えば、同僚が欠勤すると、自分の休みを返上してカバーに入ることが求められることもあります。
仮に休みを取れても、心身のリフレッシュが難しいと感じることがあります。仕事中は常に子どもや保護者への対応に追われ、自分の時間が確保しにくいためです。長期休暇を取りにくい環境では、疲労が抜けず、モチベーションの低下にもつながります。
このような状況を改善するには、休みやすい職場環境の整備が不可欠です。職員同士で業務を分担しやすい体制をつくるとともに、園として計画的に有休取得を促す仕組みも必要です。保育士自身も、限られた時間を活用しながらストレスを軽減する工夫が求められます。
7.書類や連絡帳の作成に多くの時間を取られる
保育士の業務には、子どもとの関わりに加えて、連絡帳や書類作成といった事務作業が含まれます。特に、連絡帳は保護者との情報共有に欠かせないため、子どもの様子や活動内容を丁寧に記録する必要があります。
こうした作業は保育の合間に行われることが多く、時間的な余裕がない中で対応せざるを得ません。行事の準備や報告書の作成が重なる日には、事務作業だけで数時間を要することもあります。
さらに、園ごとの記録フォーマットや記入ルールが細かい場合、修正や確認作業に時間がかかり、業務負担が増す要因となっています。
書類業務が過度に時間を取る状況が続くと、本来の保育業務に集中しづらくなり、子どもとの関わりにも影響を与えかねません。
8.子どもから目が離せず休憩を取れないことが多い
保育士は、子どもの安全を最優先に行動する必要があるため、業務中に目を離すことができません。特に、0~1歳児を担当する場合は、常に動き回る子どもたちを見守る必要があり、トイレや休憩を取る余裕がないことも多くあります。
子どもたちが遊んでいる間でも、トラブルやケガが起きる可能性があるため気が抜けず、精神的にも緊張が続きます。
集団での活動中は事故のリスクも高まり、状況に即応できる体制が求められます。その結果、保育士自身の疲労が蓄積し、体調やメンタルに悪影響を及ぼすケースもあります。
休憩を後回しにすることが常態化すれば、心身の負担は増す一方です。保育の質を保つには、職員が適切に休める環境が不可欠です。
9.園の方針と自分の考えにギャップを感じることがある
保育士として働く中で、園の方針と自身の保育観にズレを感じることは少なくありません。例えば「自由な遊び」を重視する園で働いている保育士が、「規律や集団行動を大切にすべき」と考えている場合、日々の関わり方に戸惑いが生じます。
また、園の方針は保護者対応にも影響します。保護者が希望する教育方針と園の方針が異なると、保育士はその間に立ち、調整を求められることがあります。その際、保育士自身の信念ともぶつかると、強いストレスを感じる原因になります。
さらに、園の方針が変更された場合には、従来のやり方を見直す必要があり、業務への適応に苦労することもあります。
10.日々の業務で体力的に限界を感じることがある
保育士の仕事は体力的な負担が大きく、日々の業務で限界を感じることがあります。子どもと一緒に遊んだり、お昼寝の準備、食事や排泄の介助など、常に体を動かし続ける場面が多く、特に乳児クラスでは抱っこやおんぶの時間が長くなりがちです。
さらに、安全確保のため常に緊張感を持って行動する必要があり、精神的な疲労も積み重なります。長時間勤務や頻繁な残業が続くと、体力の回復が追いつかず、疲労が慢性化していきます。
体力が限界に近づくと、子どもへの接し方に余裕がなくなり、保育の質にも影響を及ぼす可能性があります。本来の関わりを保つためには、休憩やリフレッシュの時間が欠かせませんが、忙しい現場では確保が難しいのが現状です。
このように、保育士にはさまざまな大変さがあります。以下の記事も参考にしてみてください。
参考:保育士の悩みランキング!人間関係、仕事量、待遇における解決策は? | たまごだるま TamagoDaruma
参考:保育士は何歳まで働ける?定年年齢や長く活躍するコツを解説 | ウィルオブスタイル
また、長時間労働や人間関係の悩みから「もう少し働きやすい環境に変えたい」と考えている方には、転職エージェントを活用して自分に合った職場を探すのもひとつの方法です。
参考:保育士転職エージェントおすすめ比較11選!口コミのいいエージェントも解説します! | ひとキャリ
【年齢別】保育士をやっていて大変なこと

保育士の仕事は、子どもたちの成長を支える重要な役割を担っていますが、年齢によって直面する課題は異なります。
ここでは、0歳児から5歳児までの年齢別に、保育士が感じる大変なことを具体的に見ていきましょう。
0歳児〜1歳児|つきっきりの保育に気を張る毎日が続くと感じる
0歳児から1歳児の保育は、特に目が離せない時期です。この年齢の子どもたちは、自分の意思を言葉で表現することができず、感情や欲求を泣いたり、身体で表現したりします。
そのため、保育士は常に子どもたちの様子を観察し、適切な対応をする必要があります。例えば、泣いている子どもがいると、何が原因なのかを瞬時に判断しなければなりません。
おむつが濡れているのか、眠たいのか、あるいはお腹が空いているのか、さまざまな可能性を考慮しながら行動することが求められます。
また、この年齢の子どもたちは、好奇心旺盛で動き回ることが多く、事故を防ぐためにも目を離すことができません。保育士は、子どもたちが安全に遊べる環境を整えつつ、常に注意を払う必要があります。
2歳児〜3歳児|イヤイヤ期の対応に困ることがあると感じる
2歳から3歳の子どもたちは、成長の過程で「イヤイヤ期」と呼ばれる時期を迎えます。
この時期は、自我が芽生え始め、自分の意見や気持ちを表現することが増えるため、保育士にとっては特に難しい時期でもあります。子どもたちが「イヤ!」と拒否する場面は日常茶飯事で、食事や着替え、遊びの時間などさまざまな場面で見られます。
このような状況に直面すると、保育士はどう対応すればよいのか悩むことが多いです。例えば、子どもが食事を拒否した場合、無理に食べさせようとすると逆効果になることがあります。
そのため、子どもが自分で選べるように、食材をいくつか用意しておくなどの工夫が求められます。また、遊びの時間においても、他の子どもとトラブルになることが多く、仲裁やフォローが必要になることもあります。
さらに、イヤイヤ期の子どもたちは感情の起伏が激しく、時には大泣きすることもあります。保育士は冷静に対応し、子どもたちの気持ちを受け止めることが重要です。
イヤイヤ期の対処方法については、以下の記事も参考になります。ぜひご覧ください。
参考:保育士経験者が伝授。イヤイヤ期の乗り越え方と対処方法。 | PiQUALE(ピカーレ)
参考:イヤイヤ期はいつからいつまで?イヤイヤ期の接し方とダメな対応方法を知って乗り越えよう – SHUFUFU(しゅふふ)
4歳児〜5歳児|やる気とトラブルが入り混じる毎日に戸惑うことがある
4歳児から5歳児の保育は、子どもたちの成長が著しい時期であり、やる気に満ちた姿が見られる一方で、トラブルも多く発生します。この年齢の子どもたちは、自分の意見をしっかり持ち始め、友達との関わりも活発になりますが、感情の起伏が激しく、時には衝突が生じることもあります。
例えば、遊びの中でのトラブルは日常茶飯事です。お気に入りのおもちゃを巡っての争い、遊び方の違いからくる意見の対立など、保育士としてはその場をうまく取り持つ必要があります。
しかし、子どもたちの感情を理解し、適切に対応することは簡単ではありません。時には、子どもたちの気持ちを尊重しつつ、どのように解決策を提示するかに悩むこともあります。
【役職別】保育士をやっていて大変なこと

保育士の役職によって、直面する課題や大変さは異なります。ここでは、フリー保育士、派遣保育士、クラス担任、主任保育士、そして園長というそれぞれの役職における具体的な悩みやエピソードを紹介します。
フリー保育士|毎日違うクラスで戸惑うことがある
フリー保育士は、毎日異なるクラスを担当するため、適応力が求められます。子どもたちの性格や行動パターンを短時間で把握する必要があり、初めてのクラスでは接し方に迷うこともあります。
また、クラスごとに保育方針やルールが異なり、対応を変える柔軟性が必要です。たとえば、あるクラスでは保育士主導の関わり方が求められる一方、別のクラスでは子ども主体の見守りを重視するなど、対応の幅が広がります。
さらに、担任や他のフリー保育士との情報共有が不十分だと、引き継ぎ不足から戸惑う場面もあります。スムーズな連携のためには、自ら積極的にコミュニケーションを取り、状況に応じて柔軟に動くことが欠かせません。
派遣保育士|人間関係の距離感に悩むことがある
派遣保育士は、勤務期間が限られているため、人間関係の構築に難しさを感じることがあります。特に初めての職場では、常勤保育士との関係が浅く、業務上の情報共有や相談がしづらいと感じることもあります。
また、すでに出来上がった職場の人間関係に入るには気を遣う場面が多く、会話に入りにくかったり、意見を出しづらかったりすることもあります。こうした距離感が孤独感やストレスの原因となり、業務への意欲にも影響を及ぼすことがあります。
保護者との関係構築も難しく、短期間で信頼を得るのは容易ではありません。特に子どもに関する報告や相談では、保護者の信頼を得られていないと伝え方に悩むことがあります。
クラス担任|責任の重さにプレッシャーを感じることがある
クラス担任は、子どもの安全・健康・発達に対して日常的に責任を負う立場です。そのため、一つひとつの判断や対応に大きな重みがあり、プレッシャーを感じる場面も多くあります。
例えば、けがやトラブルが起きた際には、保護者への報告や説明が求められ、対応を誤れば信頼を失う可能性があります。また、子どもの行動や成長の過程を見極め、適切な指導を行う必要があるため、「この対応でよかったのか」と自問する場面も少なくありません。
さらに、日常業務と並行して研修や勉強会への参加が求められ、スキル向上の負担も加わります。時間に追われながらも質の高い保育を維持することは、大きな精神的負荷となります。
主任保育士|現場と上司の板挟みになるときがある
主任保育士は、現場の保育士を支えつつ、園全体の運営にも関与する重要な役割を担っています。そのため、現場の意見と上司の方針の間で調整役となることが多く、板挟みになる場面もあります。
例えば、保育士が提案する保育活動が、上司の方針と食い違う場合、どちらの立場にも配慮しながら調整しなければなりません。また、保護者からの要望に対して、現場の実情を踏まえて判断し、必要に応じて保育士と上司の双方に説明や対応を求めることもあります。
さらに、現場のトラブルや人間関係の悩みを抱える保育士を支援しながら、園の運営状況を上司に報告する必要があり、精神的な負担も大きくなりがちです。
園長|判断の重さに迷うことがある
園長は、園全体の運営や方針を決定する責任を担っており、日々の業務で重要な判断を求められます。特に、保育士や保護者、地域社会との関係を考慮したうえでの決断は、簡単ではありません。
例えば、安全対策を検討する際は、リスクの程度や発生時の影響を見極めたうえで、予算や人員配置を調整する必要があります。また、保護者の要望が多様化する中で、すべてに対応することは難しく、どの声を優先するか迷う場面もあります。
方針を決める際は職員の意見を尊重しつつ、最終的な責任は園長が負うため、精神的な負担も大きくなりがちです。特に新しい取り組みでは、成果が見えるまでの不安も伴います。
保育士で大変なことは「ICTシステム」の活用で軽減できる!

保育士は、保育だけでなく事務作業や保護者対応など幅広い業務を担っており、日々多くの負担を感じています。近年はICT(情報通信技術)の導入が進み、こうした負担を軽減する手段として注目されています。
例えば、連絡帳や保育記録の作成を効率化できるアプリを活用することで、手書き作業にかかる時間を短縮でき、子どもと向き合う時間を確保しやすくなります。また、保護者との連絡もアプリ上で行うことで、伝達ミスの防止や迅速な対応が可能になり、精神的なプレッシャーの軽減にもつながります。
さらに、フリー保育士や派遣保育士が別のクラスを担当する際も、ICTを通じて保育内容や子どもの情報を共有できるため、業務の引き継ぎがスムーズになり、不安や戸惑いを減らす効果が期待できます。
ICTの活用は、保育士の業務負担を減らすだけでなく、保育の質向上にも貢献します。保育ICT導入のための補助金が国や自治体から交付されていることもあり、今後も技術の進化とともに、保育現場の働き方改革が一層進むでしょう。
まとめ
保育士は子どもたちの成長を支える重要な存在ですが、接し方や保護者対応、人間関係など、日々の業務の中で多くの悩みや負担を抱えています。年齢や役職によってその大変さは異なり、それぞれに応じたサポートが必要です。
近年では国や自治体の支援もあってICTシステムの導入が進み、業務の効率化が期待される一方で、現場の実情に即した改善も求められています。保育士が安心して働ける環境づくりは、子どもの健やかな成長にも直結します。