
子どもたちが小学校へと進むまでに育んでほしい力を示す「10の姿」は、保育や教育現場で重要な役割を果たします。これは単なる目標ではなく、一人ひとりの成長を支える道しるべです。保育士はこの10の視点を通して子どもたちの多様な個性を理解し、日々の保育活動に活かしています。
本記事では、「10の姿」が保育においてどのように機能しているのか、具体例を交えながら分かりやすく解説します。
目次
保育における10の姿とは?

「10の姿」とは、子どもたちが小学校に進むまでに育んでほしい力や資質を示す指標であり、保育・教育現場において非常に重要な役割を果たします。
これらは、子どもたちが成長する過程で必要な基盤を形成するものであり、単なる目標設定にとどまらず、日々の保育活動において具体的な指針となります。
10の姿の具体的な構成は、下記の通りです。
- 健康な心と体
- 自立心
- 協同性
- 道徳性・規範意識の芽生え
- 社会生活との関わり
- 思考力の芽生え
- 自然との関わり・生命尊重
- 数量や図形・文字などへの関心
- 言葉による伝え合い
- 豊かな感性と表現
10の姿は、子どもたちが社会で生きていくために必要な力を育むための道しるべです。保育士は、この視点を通じて子どもたちの個性や成長を理解し、支援していくことが求められます。
参考:厚生労働省「保育所保育指針解説」
参考:文部科学省「幼稚園教育要領解説」
保育において10の姿が果たす役割

10の姿は、子どもたちが自立した個人として成長するための基盤を築く役割を果たします。
例えば、健康な心と体を育むことは、子どもたちが日常生活を楽しむための基本です。また、自立心を育てることで、子どもたちは自分の意見を持ち、他者との関わりを深められます。
さらに、協同性や道徳性・規範意識の芽生えは、社会生活において必要不可欠なスキルです。これらの姿を意識することで、子どもたちは友達との関係を築き、共に遊び、学ぶことができるようになります。
保育士は、10の姿を日々の活動に組み込むことで、子どもたちの成長を促進し、より良い社会の一員としての基盤を築く手助けをしています。
保育における10の姿の内容【具体例つき】
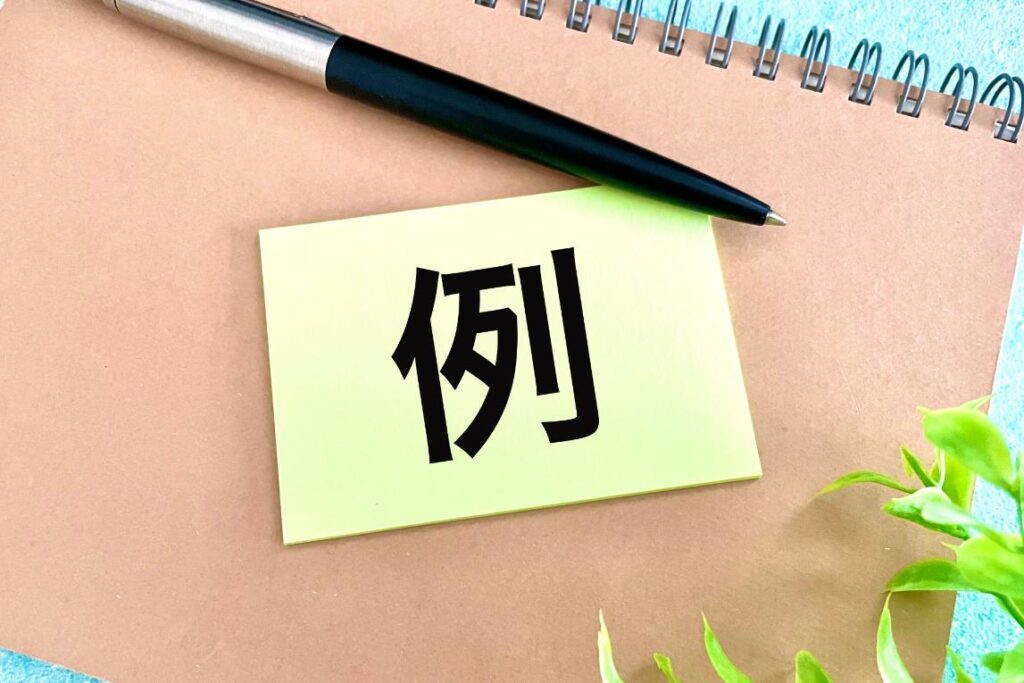
10の姿は、保育の現場で具体的な活動を通じて実践され、子どもたちの成長を支える重要な要素となっています。ここでは、保育における10の姿の内容について具体例つきで紹介します。
1.健康な心と体
「健康な心と体」は、保育所の生活の中で子どもたちが充実感を持ちながら、自分のやりたいことに向かって心と体を十分に働かせることを目的としています。
具体的には、見通しを持って行動し、自ら健康で安全な生活を築く力を育むことが求められます。これは、子どもたちが日々の生活の中で自然に学んでいくものです。
例えば、食べ物への興味関心を持ち、進んで食べようとする姿勢や、意欲的に体を動かして遊ぶことが挙げられます。これらの行動は、子どもたちが自分の健康を意識し、積極的に生活習慣を身につけるための第一歩です。
保育士は、基本的な生活習慣を身につけられるような援助を心がけましょう。食事の時間に栄養バランスを考えたメニューを提供したり、遊びの中で体を動かす機会を増やしたりすることで、子どもたちが健康な心と体を育む手助けができます。
2.自立心
自立心は、子どもが自分の力で物事を考え、行動するための基盤となる要素です。
例えば、自分で着替えをしたり、食事を自分で用意したりすることを通じて、自己管理能力を高められます。自分の選択に責任を持つことを学べるため、自己肯定感を育めます。
保育士は、子どもたちが自立心を持つための環境を整えることも大切です。自由遊びの時間を設けることで、子どもたちは自分の興味や関心に基づいて遊びを選び、友達と協力しながら問題を解決する経験を積むことができます。
また、自立心を育むには、失敗を恐れずに挑戦する姿勢も重要です。保育士は、子どもたちが失敗を経験した際、その経験をポジティブに捉えられるようサポートし、次の挑戦への意欲を引き出しましょう。
3.協同性
協同性は、子どもたちが友達と関わる中で、互いの思いや考えを共有し、共通の目的を実現するために考えたり工夫したり、協力したりする力を育む重要な要素です。
協同性を育むことで、子どもたちは充実感を持って物事をやり遂げることができるようになります。具体的には、クラスで共通の目的を持ち、役割分担を行うことで、協力して活動する経験を積むことができます。
未満児クラスでは、自分の気持ちをうまく伝えられずにトラブルになることも少なくありません。例えば、遊びの中で「自分はこれをしたい」と思っても、言葉で表現できずに友達と衝突してしまうことがあります。
このような場面では、保育士が仲立ちとなり、子どもたちが互いの気持ちを理解し合えるように援助しましょう。
4.道徳性・規範意識の芽生え
道徳性・規範意識の芽生えは、子どもたちが友達との関わりを通じて、何が許される行動であり、何が許されない行動であるかを理解する重要なプロセスです。
この段階では、子どもたちは自分の行動を振り返り、他者の気持ちに共感する力を育んでいきます。具体的には、友達の立場に立って考えたり、ルールを守ることの大切さを学んだりします。
例えば、遊びの中で子どもたちが共有するおもちゃを大切に扱うことや、友達と意見が対立した際にどう折り合いをつけるかを考える場面が多く見られます。
保育士は、子どもたちが自分の気持ちを表現できるようにサポートし、トラブルが発生した際には仲立ちをしましょう。
5.社会生活との関わり
「社会生活との関わり」は、子どもたちが他者との関係を築くうえで重要な要素です。この姿勢を育むことで、家族や地域の人々とのつながりを深め、社会の一員としての自覚を持つようになります。
具体的には、家族を大切にする気持ちを育てるとともに、地域の身近な人々と触れ合う中で、さまざまな関わり方に気づくことが可能です。
例えば、地域のイベントに参加したり、近所の人と交流することで、子どもたちは相手の気持ちを考えながら関わることを学びます。このような経験を通じて、自分が誰かの役に立つ喜びを感じたり、地域に対する親しみを持つようになるでしょう。
6.思考力の芽生え
思考力の芽生えは、子どもたちが自らの考えを深め、問題解決に向けてのアプローチを学べる要素です。保育現場では、子どもたちが自分の意見を持ち、それを表現する機会を提供することが求められます。
例えば、グループ活動や自由遊びの中で、子どもたちが互いに意見を交わし合うことで、思考力が育まれます。
具体的には、ブロック遊びを通じて、子どもたちが「どうしたら高い塔が作れるか?」と考える場面が挙げられます。このような活動では、試行錯誤を繰り返しながら、論理的に考える力や創造力が養われます。
また、保育士が子どもたちに質問を投げかけることで、より深い思考を促すことも可能です。「どうしてそう思ったの?」や「他にどんな方法があるかな?」といった問いかけは、子どもたちの思考を刺激し、自分の考えを整理する手助けとなります。
7.自然との関わり・生命尊重
「自然との関わり・生命尊重」は、子どもたちが自然の変化を感じ取り、好奇心や探究心を育むことを目的としています。
身近な事象への関心を高められるため、自然への愛情や畏敬の念を抱くようになります。具体的な例として、季節ごとの自然に触れる活動が挙げられます。
- 春……花が咲く様子を観察
- 夏……虫取り
- 秋……落ち葉を集める
- 冬……雪遊び
これらの体験を通じて、自然への興味が育まれ、動植物を大切にする気持ちが養われます。
また、遊びの中で生き物や自然と触れ合うことも重要です。例えば、園庭での植物の世話や、近くの公園での観察活動を通じて、子どもたちは自然との関わりを深めていきます。
積極的に戸外遊びを取り入れて、子どもたちの自然への興味を引き出しましょう。
8.数量や図形・文字などへの関心
子どもたちが数量や図形、文字に対する関心を持つことは、学びの基盤を築くうえで重要です。この関心は、日常生活の中で自然に育まれるものであり、保育士はその環境を整える役割を担っています。
例えば、遊びの中で数を数えたり、形を認識したりする活動を取り入れることで、子どもたちは楽しみながら学ぶことができます。
具体的には、積み木やパズルを使った遊びが効果的です。積み木を積むことで、子どもたちは数量感覚や空間認識を養うことができます。
また、パズルを通して図形の認識や論理的思考を促進できます。さらに、絵本の読み聞かせを通じて文字への興味を引き出すことも大切です。物語の中で出てくる言葉や文字に触れることで、自然と文字への関心が高まります。
9.言葉による伝え合い
「言葉による伝え合い」は、保育士や友達とのコミュニケーションを通じて、子どもたちが心を通わせる力を育むことを目的としています。
例えば、絵本や物語を楽しむことで、子どもたちは言葉や表現を自然と身につけていきます。そして、自分の体験や考えたことを言葉で伝えたり、相手の話をしっかり聞いたりする力が育まれます。
特に、言葉がまだうまく話せない0〜2歳児クラスにとって、絵本を通じて発語への意欲を育むことが重要です。保育士が絵本を読み聞かせることで、子どもたちは新しい言葉を吸収し、物語の世界観を共有する楽しさを体験します。
また、子どもたちが自分の思いを代弁することや、状況に応じた言葉の使い方を学ぶことも大切です。保育士は、子どもたちが自分の気持ちや考えを表現できるようにサポートし、言葉によるコミュニケーションを楽しむ環境を整えましょう。
10.豊かな感性と表現
「豊かな感性と表現」は、子どもたちが心を動かす出来事に触れ、感性を働かせる中で育まれる要素です。
この姿は、様々な素材の特徴や表現の仕方に気付き、感じたことや考えたことを自分自身で表現する力を養うことを目的としています。子どもたちは、友達同士での表現を楽しむ過程を通じて表現する喜びを味わい、意欲を高めていきます。
具体的には、子どもたちが感じたことや考えたことを想像力豊かに表現する機会を提供することが大切です。例えば、保育士は日々の生活の中で、子どもたちが感情を表現したいという欲求を高めるために、さまざまな道具や材料を揃えておくことが求められます。
劇を行う際は、小道具や材料を豊富に用意し、子どもたちが自由にアイデアを出しやすい環境をつくるとよいでしょう。
保育で「10の姿」をうまく活用するポイント

「10の姿」を保育において効果的に活用するためには、いくつかのポイントを押さえることが重要です。「10の姿」を効果的に活用し、子どもたちの成長を支えましょう。
続いて、保育で「10の姿」をうまく活用するポイントを紹介します。
目標ではなく成長の方向性として捉える
「10の姿」は、保育士が子どもたちの成長を支えるための指針ですが、単なる目標として捉えるのではなく、成長の方向性として理解することが大切です。
子どもたちはそれぞれ異なるペースで成長し、個性や背景も多様です。そのため、保育士は「10の姿」を通じて、子ども一人ひとりの特性やニーズを把握し、適切な支援を行う必要があります。
例えば、健康な心と体を育むためには、日々の活動の中で運動や遊びを取り入れることが重要です。しかし、すべての子どもが同じように運動を楽しむわけではありません。
ある子どもは外での遊びを好む一方、別の子どもは室内での創作活動に興味を持つかもしれません。保育士は、子どもたちの興味や関心に応じた活動を提供し、成長を見守りましょう。
小学校とのつながりを意識する
保育現場において「10の姿」を活用する際、小学校とのつながりを意識することは非常に重要です。
子どもたちが小学校に進学する際、保育で培った力や経験がそのまま活かされることが期待されます。そのため、保育士は日々の活動を通じて、子どもたちが小学校で求められる力を自然に身につけられるよう工夫する必要があります。
例えば、協同性や自立心を育むためのグループ活動を行う際、将来的に小学校での集団活動や自主的な学びに繋がるような内容を取り入れることが効果的です。
また、言葉による伝え合いを促進するために、絵本の読み聞かせやお話し会を通じて、コミュニケーション能力を高めることも重要です。これにより、子どもたちは小学校での友達との関わりや教師とのコミュニケーションに自信を持って臨めるでしょう。
まとめ
保育においての「10の姿」は、子どもたちの健やかな成長を支えるための大切な指針です。
心と体の健康、自立心、協同性、思考力、表現力など、多方面にわたる力を育むことで、子どもは社会の中で自分らしく生きる力を身につけていきます。
保育士はこの視点を持ち、日々の保育の中で一人ひとりの成長を丁寧に支え続けましょう。
