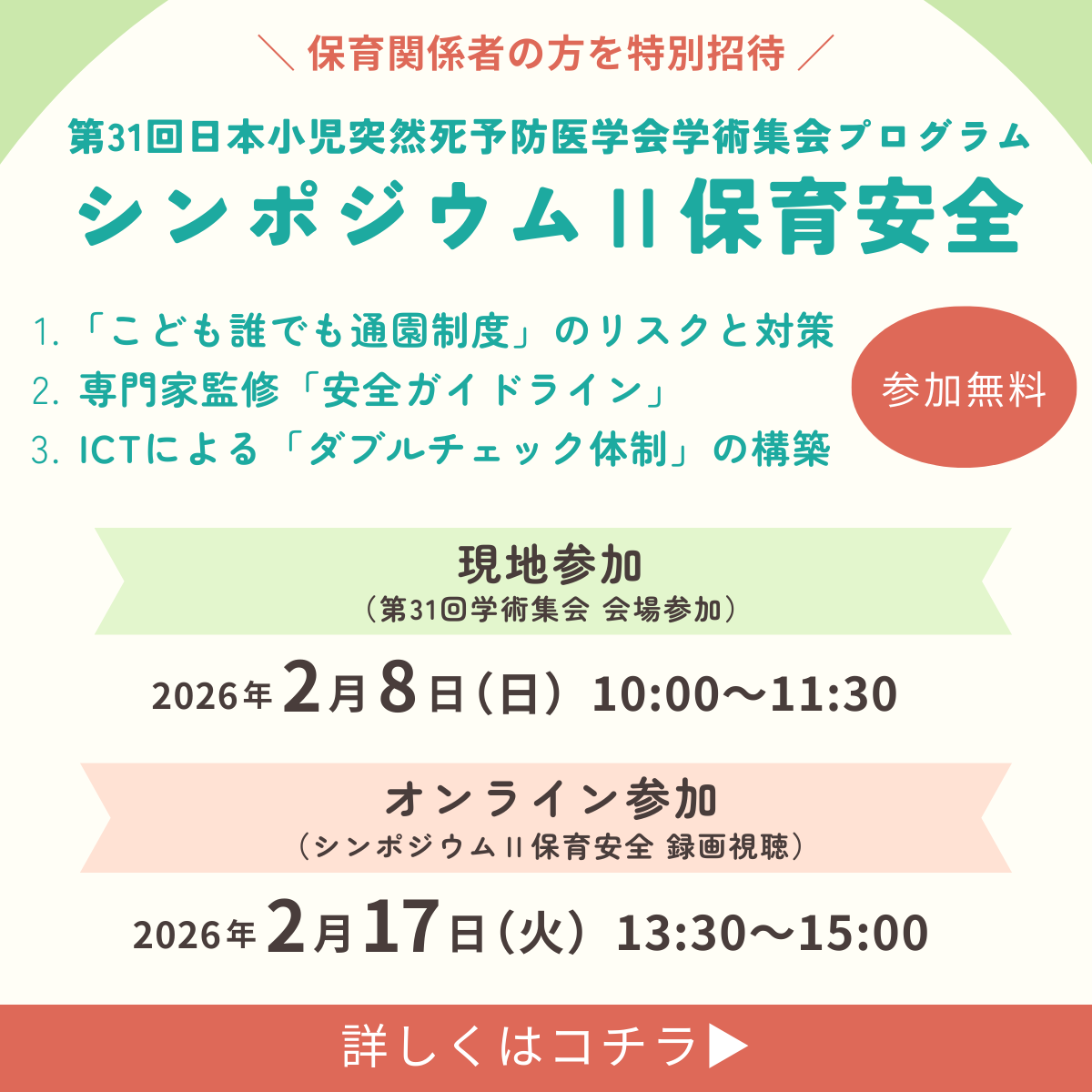子どもの障がいの有無や年齢・発達の違い、国籍に関係なく、すべての子どもが一緒に育ち合うことを目指すのが「インクルーシブ保育」です。近年は、共生社会の実現に向けた取り組みの一環として、保育現場でも注目が高まっています。
この記事では、インクルーシブ保育についてや取り組む際の重要なポイント、保育士や子どもにとってのメリット・デメリットなどについて紹介します。
目次
インクルーシブ保育とは?

インクルーシブ保育とは、障がいの有無や年齢・発達の違い、国籍にかかわらず、すべての子どもが同じ場で育ち合うことを目指す保育のあり方です。多様な子ども同士が関わりながら生活することで、互いの違いを理解し、社会性や協調性を育むことが期待されています。
この保育では、一人ひとりの個性や特性を尊重し、誰もが安心して過ごせる環境づくりが重視されます。例えば、障がいのある子どもが通常の保育活動に参加できるよう、保育士が個別の配慮や支援を行います。子どもは自分のペースで活動しながら、他者との関わりを通じて成長することができます。
このような環境で育った子どもは、多様性を自然に受け入れ、人との違いを尊重する姿勢を身につけることができます。
また、幼稚園や小学校以降のインクルーシブ教育についてもご興味ある方は、こちらの記事が参考になります。
参考:インクルーシブ教育とは?実は“すべての子”が関係する教育の最前線を解説|塾選ジャーナル
インクルーシブ保育における5つの大切なこと
インクルーシブ保育を実践するためには、いくつかの重要なポイントがあります。これらのポイントを理解し、実践することで、すべての子どもが安心して成長できる環境を整えることができます。
ここでは、インクルーシブ保育で大切な5つの要素を紹介します。
1.誰もが挑戦できる環境を整える
インクルーシブ保育では、すべての子どもが自分のペースで挑戦できる環境を整えることが基本となります。障がいの有無や発達の違いにかかわらず、子ども一人ひとりが安心して活動に取り組める場を用意することが大切です。
具体的には、遊具や教材を選ぶ際に「視覚・聴覚・運動機能」など、多様な特性に配慮したものを取り入れます。また、活動内容も年齢や発達段階に応じて段階的に設定し、無理なく取り組めるよう工夫すると良いでしょう。
また、保育士は子どもの意欲を尊重しながら、必要に応じてさりげなく支援を行う必要があります。過度に手を貸すのではなく、自分の力で達成感を得られるようサポートすることが求められます。
2.一人ひとりの育ちを受け止める
インクルーシブ保育では、子ども一人ひとりの育ちを理解し、その違いを尊重することが欠かせません。子どもたちはそれぞれ異なる背景や発達のペース、興味関心を持っており、画一的な関わりでは十分な支援ができないためです。
例えば、言葉の発達がゆっくりな子どもには、やり取りが生まれる遊びを通じて、自然に言葉を使う場面を増やす工夫が有効です。また、特定の分野に強い関心を示す子どもには、その興味を活かした活動を通じて意欲や学びを広げられます。
3.子どもの気持ちに寄り添う
インクルーシブ保育では、子ども一人ひとりの気持ちに寄り添うことが欠かせません。障がいや発達の違いにかかわらず、子どもはそれぞれ異なる背景や経験を持っており、その感情やニーズを丁寧に受け止める必要があります。
保育士は、子どもの表情や行動から気持ちをくみ取り、対話を通じて理解を深めます。例えば、不安を抱えている子どもには、共感の言葉や落ち着ける環境を用意することで、安心して過ごせるようにします。
また、子どもが自由に思いを話せる時間や空間を設けることも、自己表現の促進につながります。
さらに、子どもの感情を理解するためには、保護者との連携も重要です。家庭での様子や子どもの特性について情報を共有し、それを保育に活かすことで、より的確な支援が可能になります。
4.保護者や地域と連携しながら支える
インクルーシブ保育を効果的に進めるには、保護者や地域との連携が欠かせません。保護者は子どもの特性や生活の様子を最もよく知る存在であり、日常のやりとりを通じて情報を共有することで、保育現場での支援の質が高まります。
また、地域の支援機関や専門職との協力も重要です。例えば、発達支援センターや医療機関、ボランティア団体などと連携することで、保育士だけでは対応が難しいケースにも柔軟に対応できます。
外部の専門家を招いて観察や助言を受けるといった支援体制の構築も有効です。さらに、保護者や地域住民が参加できるイベントや勉強会を企画することで、相互理解が深まり、子どもを取り巻く環境づくりにもつながります。
5.自立へ向かう力が育つよう働きかける
インクルーシブ保育では、子どもが自分の力で考え、行動できるよう促すことが大切です。そのため、日常の中で自立につながる機会を意識的に取り入れる必要があります。
例えば、遊びや活動の場面で自分の遊びを選んだり、食事の際に自分で食器を用意したりすることで「自分で決める力」が育ちます。また、失敗を恐れずに挑戦できる環境を整えることも重要です。
保育士は、子どもの小さな挑戦を見逃さず、必要なときにそっと支えることで、自信と達成感を積み重ねられるようにします。さらに、グループ活動や共同作業を通じて、他者との関わり方や責任感を学ぶことも自立につながります。
インクルーシブ保育のメリット
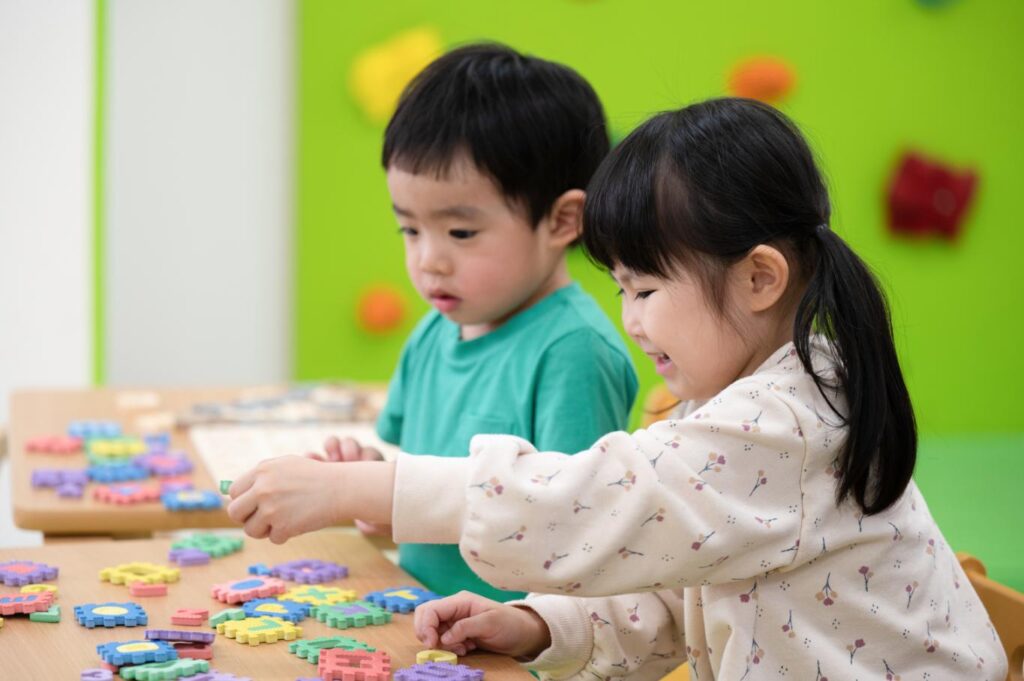
インクルーシブ保育は、子どもや保育士にとって多くのメリットがあります。ここでは、インクルーシブ保育のメリットを紹介します。
子どものメリット
インクルーシブ保育は、自分と他人の違いに気づけたり多様な存在を自然に受け入れられるようになったりと、子どもに対してさまざまなメリットがあります。
インクルーシブ保育により子どもが得られるメリットについて、具体的に紹介します。
自分と他人の違いに気づける
インクルーシブ保育では、多様な背景を持つ子どもたちと共に過ごす中で、自分と他人の違いに自然と気づくようになります。例えば、友だちが自分とは異なる方法で遊んでいたり、発言や行動のペースが違っていたりする場面に出会うことで「同じではない」という感覚を持つようになります。
このような気づきは、単に違いを知るだけでなく、自分の考え方や感じ方を客観的に見るきっかけにもなります。相手を尊重する姿勢の基礎となり、集団生活を円滑に送るうえで大切な第一歩となります。
多様な存在を自然に受け入れられるようになる
インクルーシブ保育により、日常的にさまざまな子どもと関わるため、子どもたちは違いを特別なものとせず、自然に受け入れる感覚を育てていきます。例えば、特別な支援が必要な友だちが一緒に活動する中で「みんなが同じようにできなくても大丈夫」という価値観が浸透していきます。
こうした日常を通じて、子どもたちは他者に対する偏見や先入観を持ちにくくなり、多様性を前向きに捉える力を育みます。インクルーシブ保育の環境そのものが、違いを認め合う態度を無理なく形成していく土台となります。
異なる立場の人との関わり方を学べる
インクルーシブ保育により、さまざまな特性を持つ子どもと関わるため、子どもたちは相手の立場を意識したコミュニケーションの方法を学べます。例えば、言葉でのやり取りが難しい友だちと関わる場面では、表情や身ぶりで気持ちを伝える工夫が必要になります。
このような関わりを重ねることで、子どもたちは一方通行ではない相互理解の姿勢を身につけられます。相手の状態を観察し、自分の伝え方を柔軟に調整する経験は、実践的な対人スキルの習得につながります。
柔軟に対応する力が育つ
インクルーシブ保育では、子どもたちが日常的に多様な価値観や行動様式に触れることで、状況に応じて考え方や行動を変える力が育ちます。例えば、特定の活動に苦手意識のある友だちがいた場合、その子に配慮した遊び方を提案するなど、相手に合わせて自分の行動を調整する経験が増えます。
こうした対応を繰り返すことで、子どもたちは一律のやり方にこだわらず、場面に応じた柔軟な選択ができるようになります。これは、日々の保育活動に限らず、将来の多様な人間関係や社会生活でも活きる力となります。
チームワークや社会性を学べる
インクルーシブ保育では、異なる特性を持つ仲間と協力して活動する経験を重ねる中で、自然とチームワークや社会性が育ちます。例えば、グループでの制作や役割分担のある遊びを通じて、自分の役割を果たしながら相手に配慮する力が養われます。
また、上手くいかないときに友だちと話し合って解決策を見つける過程は、社会的なルールや対話の重要性を理解する機会となります。これにより、子どもたちは集団の中で協調して行動する力を身につけられます。
保育士のメリット
インクルーシブ保育は、保育士自身の成長にも寄与する重要な取り組みです。インクルーシブ保育により保育士が得られるメリットについて、具体的に紹介します。
保育の専門性を高められる
インクルーシブ保育の実践は、保育士の専門性を高める大きな機会となります。障がいや発達の特性を持つ子どもと日常的に関わる中で、支援の工夫や柔軟な教育方法を実践的に学ぶことが可能です。
また、個々の子どもの行動や反応を丁寧に観察し、適切な対応をする力も求められるため、観察力や判断力が養われます。加えて、子どもとの信頼関係づくりや保護者との継続的な情報共有を通じて、コミュニケーション能力や家庭支援の視点も深まります。
子どもに寄り添う力がつく
インクルーシブ保育では、保育士が多様な特性を持つ子どもと関わる中で、一人ひとりの気持ちや行動の背景を理解しようとする姿勢が求められます。この実践を通じて、子どもの感情や反応を丁寧に読み取り、適切に対応する力が養われます。
また、保育士の共感的な関わりは、子どもが安心して自己を表現するための土台となります。保育士が理解や思いやりを示すことで、子どもたちも他者の気持ちに目を向け、思いやりを持って接する態度が育ちます。
保護者との信頼関係を深められる
インクルーシブ保育では、保護者との信頼関係が不可欠です。子どもの発達を支えるうえで、保育士と保護者が情報を共有し、協力体制を築くことが重要です。
日々のやり取りや定期的な面談を通じて、子どもの様子や支援の方針を伝えることで、保護者の不安を軽減し、信頼を得ることができます。
例えば、保育方針やインクルーシブ保育の目的を丁寧に説明することで、家庭と保育が一貫した姿勢で子どもを支援できるようになります。また、保護者からの意見や要望に耳を傾け、保育に反映させる姿勢は、双方向の信頼を深めるうえで効果的です。
職員間の連携が強くなる
インクルーシブ保育では、子どもの多様なニーズに対応するために、保育士同士の連携が不可欠です。支援方針や観察結果を共有し、具体的な対応を話し合うことで、より効果的な支援が可能になります。
また、日常的に情報交換を行うことで、職員間のコミュニケーションが活性化し、チームとしての一体感が生まれます。異なる経験や専門性を持つ職員が意見を出し合うことで、多角的な視点が保育に反映されるため、質の高い支援につながるでしょう。
インクルーシブ保育のデメリット

インクルーシブ保育には多くのメリットがある一方で、デメリットも無視できません。これらの課題を理解し、適切に対処することが、より良い保育環境を作るためには重要です。
ここでは、インクルーシブ保育のデメリットを紹介します。
子どものデメリット
インクルーシブ保育は多様な子どもたちが共に育つ場を提供する一方、子どもたちにとってのデメリットも存在します。子どもがインクルーシブ保育で受ける可能性があるデメリットについて具体的に紹介します。
多様な環境に順応しづらいことがある
インクルーシブ保育では、異なる発達段階や特性を持つ子どもたちが共に過ごしますが、特に障がいのある子どもにとっては、環境への順応が難しいことがあります。
例えば、感覚過敏のある子どもは、大きな音や人の多さによって強い不安やストレスを感じやすく、集団活動への参加が困難になる場合があります。また、社会的なスキルが未発達な子どもは、他の子どもと関わることに戸惑い、孤立しやすくなることもあります。
このような状況に対処するには、一人ひとりの特性を理解し、静かなスペースの確保や活動内容の調整など、個別に配慮された環境づくりが欠かせません。すべての子どもが安心して参加できる場をつくるには、丁寧な支援と柔軟な対応が求められます。
自己否定につながることがある
インクルーシブ保育では、多様な子どもが共に過ごす中で、発達や特性の違いが目立ちやすくなります。その結果、障がいのある子どもや発達がゆっくりな子どもが、周囲と自分を比較し、「自分はできない」と感じることがあります。特に繊細な子どもは、そうした経験から自己否定につながるおそれがあります。
また、周囲の理解が不十分な場合、「できない子」として見られたり、配慮がない言葉をかけられることで、自信を失うこともあります。こうした環境では、子どもが自らの価値を見いだしにくくなり、自己肯定感が下がる原因となります。
このようなリスクを防ぐには、大人が子どもの特性に配慮した支援を行い、個々の成功体験を積み重ねることが大切です。できることに目を向け、自分なりの成長を実感できる場づくりが、子どもの心の安定につながります。
刺激が物足りなく感じることもある
インクルーシブ保育では、多様な子どもたちが共に生活しますが、発達の早い子や特定の分野に強い関心を持つ子にとっては、活動の内容が簡単すぎて物足りなく感じることがあります。その結果、自分の力を発揮できず、学びの機会を逃す可能性があります。
刺激が不足すると、子どもの興味や意欲が低下し、活動への参加が消極的になることもあります。特に好奇心や表現欲求が強い子にとっては、環境が合わないことで不満やストレスを感じることがあります。
こうした課題を防ぐには、保育士が子どもの発達段階や関心に応じて活動を調整し、挑戦できる環境を整えることが必要です。子どもが自分の力を活かしながら成長できるような配慮が、インクルーシブ保育の質を高めます。
個別対応に対して不公平感や混乱が生じることがある
インクルーシブ保育では、子ども一人ひとりのニーズに応じた個別対応が欠かせません。しかし、その対応が一部の子どもだけに見える場合、他の子が「なぜ自分には特別な配慮がないのか」と不公平に感じることがあります。このような認識は、自己肯定感や集団への安心感を損なう要因になります。
また、個別支援の目的が十分に説明されていないと、子ども同士で誤解や戸惑いが生じることがあります。特定の子どもに対する特別な対応が「ずるい」「特別扱い」と見なされると、クラスの雰囲気にも悪影響を及ぼす可能性があります。
そのため、保育士は個別対応の背景や意義をわかりやすく伝え、すべての子どもが大切にされていると感じられるよう配慮することが重要です。
理解が不十分だと誤解が生まれる可能性がある
インクルーシブ保育では、子どもの特性や支援ニーズを正しく理解することが不可欠です。しかし、その理解が不十分な場合、誤解や対応ミスが生じやすくなります。
例えば、感覚過敏や注意力の特性がある子どもに適切な配慮がされないと、不安や混乱を招き、集団から孤立するおそれがあります。このような状況は、子どもの自己肯定感や社会性の発達を妨げる要因になります。
さらに、支援方針に対する認識のずれは、保育士間や保護者との連携に支障をきたすこともあります。具体的には、子どもの対応をめぐって意見が食い違うと、チームの足並みが乱れ、一貫した支援が困難になります。
こうした問題を防ぐには、職員や保護者が共通理解を持つための研修や情報共有の機会を定期的に設けることが重要です。正しい理解と連携があってこそ、多様な子どもたちが安心して成長できる保育環境が実現します。
保育士のデメリット
インクルーシブ保育を実践する際、保育士にはいくつかのデメリットが存在します。デメリットを理解し、適切なサポート体制を整えることが、インクルーシブ保育を成功させるためには重要です。
ここでは、保育士がインクルーシブ保育で受ける可能性があるデメリットについて紹介します。
高い専門性と柔軟な対応力が求められる
インクルーシブ保育では、多様な背景やニーズを持つ子どもたちに対応するため、保育士に高度な専門知識と柔軟な対応力が求められます。
障がいの特性や発達段階に応じた支援を行うには、医療や発達に関する知識、実践的な技術が必要です。そのため、保育士は継続的な学習と研修を通じて知識を深める必要があります。
また、外国籍の子どもへの対応では、言葉や文化の違い、宗教上のルールなどを知ることも大切です。
子どもは日々成長し、状況も変化します。すべての子に同じ方法が通用するわけではなく、個々の反応や状態に応じた支援の見直しが欠かせません。保育士には、状況に応じて即時に対応を切り替える柔軟性と判断力が求められます。
さらに、保護者との連携も不可欠です。家庭での様子や子どもの特性に関する情報を共有し、それを保育に反映することで、より的確な支援が可能になります。加えて、地域の専門機関や他職種との連携も、保育の質を高める重要な要素です。
保育の方法に迷いが生まれることがある
インクルーシブ保育では、子ども一人ひとりの特性や発達段階に応じた支援が求められるため、保育士が対応に迷う場面も少なくありません。
例えば、ある子どもには積極的な支援が必要でも、別の子どもには自立を促すために距離を取る方が適切な場合があります。このような判断が求められる場面では、どこまで介入すべきか迷いが生じやすくなります。
特別な支援が必要な子どもへの対応では、介入の度合いやタイミングを見極める必要があり、その一方で他の子どもとの関わりのバランスにも配慮が求められます。こうした複雑な判断は、保育士の経験や専門知識に左右され、自信を失う要因になることもあります。
このような課題に対応するには、保育士同士での情報共有や定期的な研修、外部専門家との連携が有効です。他者の視点を取り入れることで、自らの判断を見直し、適切な支援方法を見つけやすくなります。
負担が増えることがある
インクルーシブ保育では、多様な子どもに対応するため、保育士に高い専門性と柔軟な対応力が求められます。その結果、日々の業務に加え、個別支援に必要な準備や情報収集に時間を要するため、精神的・肉体的な負担が増すことがあります。
また、保育の質を保つには職員間の連携が不可欠ですが、支援方針の違いや役割分担が不明確な場合、意見の食い違いや業務の停滞が起こりやすく、保育士のストレス要因となります。
さらに、保護者対応も負担の一因です。特別な支援を求める保護者からの期待や要望に応えるには、保育士自身が専門知識や対応スキルを継続的に学ぶ必要がありますが、その時間を確保することが難しい場合もあります。
保育士の負担を減らすには、継続的な研修と業務負担の分散を図る体制づくりが不可欠です。
インクルーシブ保育の具体例
インクルーシブ保育を実践するには、具体的な取り組みが重要です。ここでは、インクルーシブ保育の具体例を紹介します。
子どもが活動に参加しやすい環境づくり
インクルーシブ保育では、すべての子どもが無理なく活動に参加できるよう、内容や進め方に配慮する必要があります。例えば、制作活動では細かい作業が苦手な子どもに対して、手でちぎれる素材や大きな道具を用意し、達成感を得やすくします。
運動遊びでは、体の動かし方に不安がある子どもには、事前に動作を個別に練習する時間を設けたり、少人数でスタートするなどの工夫を加えます。他の子どもたちには、自然に手助けできるような声かけを行い、協力しながら楽しめる雰囲気をつくると良いでしょう。
また、活動の指示が伝わりにくい子どもには、イラスト付きのスケジュールカードを活用して見通しを持たせるなど、参加しやすくなる工夫を取り入れることをおすすめします。
個々に応じた対応を行う
インクルーシブ保育では、子ども一人ひとりの発達や特性に合わせた支援が欠かせません。例えば、言葉の発達がゆっくりな子どもには、絵カードやジェスチャーを使って意図を伝えやすくするなど、コミュニケーションの工夫を取り入れます。
音や刺激に敏感な子どもには、静かなスペースでの活動を用意したり、予定変更が苦手な子どもには、スケジュールの見通しを示すカードを使って不安を軽減する工夫が有効です。また、集団行動が苦手な子どもに対しては、少人数の活動から段階的に関わりを広げることで、無理なく参加できるよう支援します。
保育士の配置で手厚く支える
インクルーシブ保育では、保育士の人数や専門性が子どもへの支援の質を左右します。特別な支援が必要な子どもには、個別に寄り添える保育士を配置し、安心して活動に参加できる体制を整えましょう。
例えば、感覚過敏のある子どもには刺激の少ない環境へ誘導したり、クールダウンの時間を確保するなど、丁寧な対応が必要です。このような支援には、十分な人員と瞬時の判断力が求められるため、保育士の配置は重要なポイントとなります。
また、障がい特性に詳しい保育士がチームにいることで、他の保育士への助言や、対応の引き出しを増やすことができ、現場全体の支援力が高まります。
インクルーシブ保育の現場では、療育(発達支援)と連携することで、よりきめ細かな支援体制を整える園も増えています。子どもの発達や特性に幅広く応えるために、「そもそも療育とは?」といった基本的な理解を深めたい方へは、以下の記事も参考になります。
参考:療育(発達支援)とは?意味や内容、受けられる施設をわかりやすく説明 | ステラ幼児教室・個別支援塾
また、子どもの気になる行動については以下の記事も参考にしてみてください。
参考:子どもの発達障害を早期発見するためのチェックポイント|スタジオそら
東京都の発達障害対応塾や放課後等デイサービスを知りたい方は、以下の検索サイトもご活用ください。
参考:発達支援ハブ|東京都の発達障害・ADHD・学習障害対応塾を探す
インクルーシブ保育の現状

インクルーシブ保育は、近年ますます重要性が増しているテーマです。特に、保育と児童発達支援を連携させた取り組みが進められており、障がいのある子どもたちがより良い環境で育つための支援が強化されています。
続いて、インクルーシブ保育の現状について紹介します。
保育と児童発達支援を連携させた取り組み
インクルーシブ保育を実現するには、保育所と児童発達支援事業所の連携が欠かせません。障がいのある子どもへの支援が求められる中、保育現場と専門機関が協力し、個々の子どもに応じた支援体制を築く取り組みが進んでいます。
具体的には、保育士と児童発達支援の専門職が定期的に情報を共有し、観察結果をもとに個別の支援計画を作成します。これにより、保育士は専門的な知見を実践に取り入れ、より効果的な支援を行えます。
また、保護者との連携も重要です。保護者が子どもの特性や支援方法を理解することで、保育と家庭の両方で一貫したサポートが可能になります。
障がい児支援のニーズが拡大している
近年、児童発達支援や放課後等デイサービスの利用者数が増えており、障がい児への支援ニーズが急速に高まっています。
背景には、多様性を尊重する社会づくりやインクルーシブ保育の普及があります。障がいのある子どもも適切な支援を受け、集団生活の中で安心して育つ環境が求められています。
参考:厚生労働省「児童発達支援・放課後等デイザービスの現状などについて」
保育現場では、障がいの特性に応じた対応が必要とされる場面が増え、保育士には専門知識や実践力が一層求められています。例えば、発達障がいのある子どもに対しては、行動の見通しを持たせるスケジュール提示や、感覚に配慮した活動設計が効果的です。
また、家庭との連携は欠かせません。保護者と情報を共有し、一貫した支援を行うことで、子どもの安定した成長を促せます。さらに、地域の支援機関との協力体制や専門家の助言を活用することで、保育現場の支援力を高められます。
まとめ
インクルーシブ保育は、すべての子どもが互いに関わり合いながら成長する環境をつくる取り組みです。一人ひとりの違いを尊重し、挑戦できる場を整えることで、共生社会への基盤が育まれます。
保育士には専門性と柔軟な対応力が求められますが、その分やりがいも大きく、信頼関係を深める機会にもなります。今後、保育現場や地域が連携し、誰もが安心して育つ環境を築くことがより一層求められるでしょう。